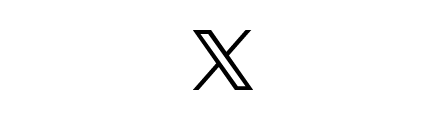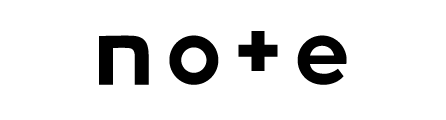- 総合TOP
- 宇宙
- AI
- ロボット
- WEB3・メタバース
海外で挑戦を続ける日本人に直接話を聞き、キャリアや価値観を深掘りしながら、世界で活躍するための実践知を探る本連載。今回登場するのは、人口の9割が外国人という都市ドバイを拠点に活動するツアーガイド/フォトグラファー 原田 篤さんだ。「世界は自分が思うよりずっと開いている」。そう語る原田さんの歩みには、未知の環境に飛び込み、越境者として生きるための具体的な示唆が詰まっている。日本、オランダ、ドバイ──三つの土地を越境しながら培われた視点を通じて、日本人がグローバルで戦うための本質に迫る。(文=JapanStep編集部)

ツアーガイド/フォトグラファー
原田 篤さん
結婚式のエンドロール撮影からキャリアをスタート。2013年にオランダ・ハーレム及びアムステルダムを拠点に、アーティストやミュージシャンの撮影に携わりながら、クラブシーンやスタジオ、プレハブ街といった個性的な空間を撮影。これまで、公益財団や企業、日本のメディア、オランダの新聞などへ写真を提供。日本のロックバンド「Guitar Wolf」のツアーフォトグラファーとしても幅広く活動。現在は、アラブ首長国連邦 ドバイに拠点を移し、都市と文化の変容、人々の営みと風景の記録に取り組む。約2年間、日本人向けのドバイツアーガイドとしても活躍。
安定を捨てた28歳。英語偏差値40から欧州へ踏み出すまで
アラブ首長国連邦・ドバイ。世界190カ国から人が集まり、街全体の9割が外国籍で構成される多国籍都市である。この超高速で変貌する都市で、ツアーガイドとして旅人を導き、フォトグラファーとして街のダイナミズムを撮り続ける日本人がいる。原田 篤さんだ。現在はドバイの都市文化と人々の営みを記録する表現者として前線に立つが、その軌跡は決して平坦ではなかった。むしろ、挫折と選択の積み重ねが生んだ「越境の物語」である。
原田さんが世界の広さを初めて実感したのは大学時代。当時の英語偏差値は40ほど。世界で働く未来など考えたこともなかったが、「現状を変えたい」という焦りだけを胸に、1ヶ月のフィリピン留学へ飛び込んだ。そこで出会ったのは、厳しい生活のなかでも他者に温かく接する人々だった。「わずか1ヶ月のフィリピン生活で、こんなにも知らない世界があるのだなと知った。世界は広いし、面白い」。この経験が、大きな越境の原点となった。その後、再びフィリピンへ留学し、英語力の強化にも力を入れた。
 20歳でフィリピン留学したバコロドの景色(写真提供=松崎 唯)
20歳でフィリピン留学したバコロドの景色(写真提供=松崎 唯)
大学卒業後は、日本企業で法人営業として働いた。毎日都心のオフィスに通い、営業電話をかけ、全国の顧客にITソリューションを提案する日々。安定したキャリアではあったが、胸の奥に違和感が残り続けた。そして芽生えたのが、もともと考えていた「30代はヨーロッパで働いてみたい」という直感だった。根拠はない。それでも、心が確かにその方向を向いた。
28歳、原田さんは賭けに出る。オランダの引越し会社に応募し、採用を勝ち取った。英語は拙く、人脈もない。それでも迷いはなかった。「家族には迷惑をかけました」と笑うが、その決断は、初めて「自分の人生のハンドル」を自分で握った瞬間だった。
だが、原田さんを待っていたのは欧州の華やかな暮らしではなかった。曖昧なビザ、休暇なし──いわゆる“グレー”な労働環境だった。原田さんはここで海外の現実に直面する。しかし泣き寝入りはしなかった。現地の弁護士を雇い、会社に対して裁判を起こす準備をして最終的に裁判にならず示談に至った。この出来事は海外で生きるために必要な「自己防衛の力」を強烈に刻みつけた。
数々の苦難にも、日本に帰国する選択肢は浮かばなかったという。「現状の延長線に未来はないと感じていたんです。だからこそ、新しい環境に踏み出す機会があるなら必ず掴むまで挑戦し続けると決めていました」。日本で働き続けていれば出会わなかった困難、そしてそこで得た学び。これらを携えながら、原田さんはフォトグラファーとして生きる道を静かに歩き始めた。
 オランダ移住当初の原田さんの撮影姿(写真提供=原田 篤)
オランダ移住当初の原田さんの撮影姿(写真提供=原田 篤)
 原田さんがフリーランスとして起業した際に、借りたアムステルダムのオフィス(Nachtlab)(写真提供=原田 篤)
原田さんがフリーランスとして起業した際に、借りたアムステルダムのオフィス(Nachtlab)(写真提供=原田 篤)
 オランダ・ハーレムの風車「Molen de Adriaan(デ・アドリアーン風車)」(写真提供=原田 篤)
オランダ・ハーレムの風車「Molen de Adriaan(デ・アドリアーン風車)」(写真提供=原田 篤)
極貧からの再起。写真が与えてくれた「言葉を超える武器」
原田さんは、若いころからフォトグラファーとして本格的に歩んできたわけではない。写真との最初の接点は趣味としてのカメラだった。とはいえ、20代の頃に結婚式のエンドロール撮影を任された経験があり、人の人生の一瞬を記録することの面白さや、映像を仕事にできるかもしれないという小さな芽は、その頃すでに胸の内に生まれていたという。しかし、日本にいる間は営業職として日々を送り、写真が職業になるとは思っていなかった。
その流れが大きく変わったのは、オランダに渡ってからだ。フリーランスとして独立した当初は順調だったものの、仕事が途絶え、空港で夜を明かす日もあった。そんな極限状態の中で、原田さんをつなぎとめたのが写真だった。カメラは単なる趣味から、異国で生き抜くための言語へと変わっていったのである。
彼が飛び込んだのは、オランダ・ハーレムのハードコアテクノシーン。文化も言語も異なる屈強な男たちの中で、原田さんは好んで2年間撮り続け、撮影した写真をアーティストへ送り続けた。そしてついに、アーティストから50ユーロの謝礼を手渡される。「お前はもう家族だ」。その言葉は、越境者として初めて得た「居場所」だった。現在も、彼らとは深い親交を結んでいる。
 オランダ・ハーレム ハードコア・テクノのチーム(HDC)との1枚(写真提供=原田 篤)
オランダ・ハーレム ハードコア・テクノのチーム(HDC)との1枚(写真提供=原田 篤)
 オランダの屋外フェスティバルでの1枚(写真提供=原田 篤)
オランダの屋外フェスティバルでの1枚(写真提供=原田 篤)
また、日本のロックバンド「Guitar Wolf」とのツアー撮影にも同行。初めてオランダのハーレムで観たステージで火花を散らすその姿に、「凄すぎて痺れた」「世界を席巻しているって、本当にこういう人たちのことだ」と衝撃を受けた。
「『Guitar Wolf』のライブを観た後にオランダ・ハーレムの街を、胸をはって大股で歩いた記憶は今でも大事にしています。そこからひたすら『Guitar Wolf』のツアースケジュールを調べ、アメリカ、ヨーロッパ、日本をカメラ片手に追いかけました。今では一緒にツアー同行を許していただけるようになりました」(原田さん)
原田さんの中に再び「海外で挑む意欲」が強く燃え上がった瞬間だった。
 2025年度のヨーロッパツアー「Guitar Wolf」のツアーファイナル(写真提供=原田 篤)
2025年度のヨーロッパツアー「Guitar Wolf」のツアーファイナル(写真提供=原田 篤)
こうした経験の中で、原田さんは日本人が海外で陥りやすい「コミュニケーションの罠」を理解していく。原田さんが英語でのコミュニケーションで重視しているのが、「相槌を打たないこと」と「Pleaseを必ず添えること」である。
日本人は、聞き取れない英語の会話でもつい「うん、うん」と頷いてしまう。しかし原田さんは言う。「分からないのに『そうだよね』って言っちゃう。これは海外では真っ先に指摘される癖です」。理解していないのに同意したように見える行動は、海外では不誠実と受け取られかねない。
さらに、自分の要望を伝える際には「Please」をできるだけつけるように心がけているという。「英語ネイティブではないと、ぶっきらぼうな表現になってしまう人が多いので、Pleaseをつけるだけで『丁寧なやつだ』と思われるんです。相槌とPlease、この2つのポイントだけ覚えてもらうだけでも、コミュニケーションは大きく変わると思いますよ」。
原田さんはまた、海外で働くうえで「体力」の重要性を強調する。異文化で働くということは、想像以上に精神的・身体的な負荷が大きい。最終的にものを言うのは、環境に踏みとどまり続ける馬力なのだ。
もう一つ、慣れない海外での挑戦で、原田さんを大きく支えてくれたのが、オランダで出会った先輩方や、同じように移住してきた日本人の存在だった。オランダで示談金を手にし、「これからどう生きるか」を見失いかけていた時期に、現地で出会ったある日本人の方は、原田さんにシンプルでクリエイティブな生き方を、言葉ではなく実践で教えてくれたという。
「一緒にいるだけで自分自身がちょっとだけ特別な存在に思えたり、温かくていつも笑顔でいて人をワクワクさせてくれたりする、本当に魅力的な方です。厳しい局面に立ったとき、その人ならどう考えるだろうかと、今でも自分に問いかけています」(原田さん)
海外では中国系など強いネットワークを持つコミュニティが多いが、「自分はたくさんの日本人に助けられた」と原田さんは語る。孤立しがちな異国の地で、同じ日本人に手を差し伸べられた経験は、前に進むための支えとなり、再起のための心理的な土台を与えた。
 原田さんが公私ともにお世話になったオランダ滞在時の藤原 康晴さん(右)(写真提供=原田 篤)
原田さんが公私ともにお世話になったオランダ滞在時の藤原 康晴さん(右)(写真提供=原田 篤)

 原田さんが現地で切磋琢磨した日本人コミュニティ同世代の友人(Yuji,So Oishi)(写真提供=原田 篤)
原田さんが現地で切磋琢磨した日本人コミュニティ同世代の友人(Yuji,So Oishi)(写真提供=原田 篤)
 原田さんがシェアハウスで一緒になり語学や生活を含めて時間を共有した友人アンドレさん(左)(写真提供=原田 篤)
原田さんがシェアハウスで一緒になり語学や生活を含めて時間を共有した友人アンドレさん(左)(写真提供=原田 篤)
 原田さんがドバイで写真使用の許諾を貰うために現地を訪問した際の一枚(Etihad museum)(写真提供=原田 篤)
原田さんがドバイで写真使用の許諾を貰うために現地を訪問した際の一枚(Etihad museum)(写真提供=原田 篤)
オランダでの活動を経て、島根県松江市に移住した。個人事業主としてフォトグラファーとして生きようとしたが、自分の甘さと理想と現実のギャップがあったと原田さんは振り返る。「実際は、その日暮らしのアルバイト生活でした。ですが、その時過ごした時間は鮮明で、かけがいのない財産になっています。お世話になった接客業の上司に働き始めた当初『そのままの生き方では人生後悔するぞ』とお言葉を頂き、そこから挨拶、掃除、洗い物、洗濯など先ずは目の前のことを人並みにできるように意識しました」(原田さん)
日中は重い荷物を運び、トラックで山陰を巡り、夜は繁華街でウェイターとして働き生計を立てながら、ようやく人並みの生活ができるようになり、徐々に撮影の仕事も増えていったという。「島根県の現場で一緒に汗をかき、接客業でコロナ禍を乗り越え、共に音楽イベントを開催したメンバー、日陰の時期にお会いした方々、厳しくも温かい言葉をかけて頂き、お世話になった皆様には、感謝の気持ちで今でも溢れます」(原田さん)
その後、社会人向けの国立島根大学のプログラムに通い、「社会教育士の資格取得」「山陰ツーリズム育成塾」「起業家スクール」など勉学に励んだ。極貧からの再起、そして諦めきれなった写真を撮る意義、勉学、日常の生活によって開かれた人間関係。そのすべてが、原田さんにとっての「越境の実践知」となっていった。
 原田さんが島根県松江市でフリーランスとして活動当初「テクノアークしまね南館」のシェアオフィスでの一枚(写真提供=原田 篤)
原田さんが島根県松江市でフリーランスとして活動当初「テクノアークしまね南館」のシェアオフィスでの一枚(写真提供=原田 篤)
 国立島根大学での社会教育士プログラムの講師・学友と写る原田さん(写真提供=原田 篤)
国立島根大学での社会教育士プログラムの講師・学友と写る原田さん(写真提供=原田 篤)