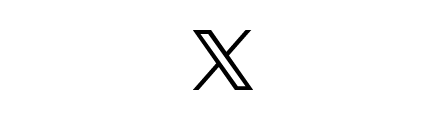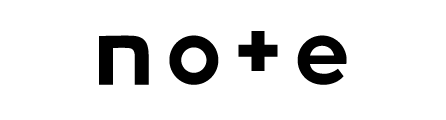- 総合TOP
- 宇宙
- AI
- ロボット
- WEB3・メタバース
海外で挑戦を続ける日本人のキャリアと価値観を掘り下げ、世界で活躍するための実践知を探る本連載。今回登場するのは、ドイツ・ザールラント大学コンピュータ・サイエンス学部でジュニア・プロフェッサーを務め、AI×教育の研究に取り組む永嶋 知紘さんだ。奈良の一般的な家庭に生まれ、英語も特別に得意ではなかった一人の永嶋さんが、米国、そしてドイツへと越境し、国際的な研究者としてのキャリアを築くまでの道のりは決して平坦ではなかった。「海外に出て初めて、自分の立ち位置と日本の強みが見えた」。そう語る永嶋さんの歩みには、安定よりも問いを選び続けた意思決定の積み重ねがある。家族とともに世界へ踏み出した研究者のリアルな経験から、これから越境を志す日本人が持つべき覚悟と可能性を読み解く。(文=JMPプロデューサー 長谷川 浩和)

ザールラント大学
コンピュータ・サイエンス学部ジュニア・プロフェッサー
永嶋 知紘さん
奈良県生まれ。国際基督教大学(ICU)教養学部卒業。2014年6月から2016年8月まで北海道大学 高等教育推進機構オープンエデュケーションセンターで特定専門職員として勤務。2016年から2017年にかけてスタンフォード大学教育大学院で修士課程、2017年から2022年までカーネギーメロン大学で博士課程研究員として研究に従事。2022年8月に同大学から博士号を取得後、2022年9月よりハーバード大学 Berkman Klein Center for Internet & Societyのファカルティ・アソシエイトに着任。2022年11月から現職。
奈良から世界へ──挫折が火をつけた越境の原点
1991年。永嶋 知紘さんは、父は会社員、母は専業主婦という、いわゆる一般的な奈良県の家庭に生まれ育った。幼少期から海外志向が強かったわけではなく、特別な英語教育を受けていたわけでもない。転機となったのは高校時代、県主催の海外交流プログラムだった。高校2年時に参加したタイでの短期交流は刺激的ではあったが、この時点では「海外で生きる」という実感までは伴っていなかったという。
意識が大きく変わったのは、その後に参加したアメリカでの国際会議型プログラムだった。ニューヨークやワシントンD.C.で、世界各国から集まった高校生たちと、環境問題や国際情勢について英語で議論する場に身を置いた。「言いたいことはあるのに、英語が出てこない。発言しようとした瞬間には、もう次の議論に移っている。ものすごく悔しく、もどかしい思いをしました」(永嶋さん)
帰国子女や留学経験者に囲まれ、当時は自分が世界の中でほとんど存在していないことを突きつけられた感覚だったという。この経験は、永嶋さんにとって最初の大きな挫折だった。
それでも同時に、「このままでは終われない」という思いが芽生えた。英語を本気で学ぶために選んだ進学先が国際基督教大学(ICU)である。奈良では知名度も高くなく、家族や周囲からは反対の声もあったが、永嶋さんの意思は揺るがなかった。
「英語ができなければ、世界で何も始まらないという強い思いで、単身上京しました」(永嶋さん)
しかし、大学進学後も違和感は消えなかった。英語力は着実に伸びた一方で、講義中心の授業スタイルに物足りなさを感じるようになる。
「学費も時間もかけて大学に来ているのに、受け身で話を聞くだけでいいのか。次第に、国際機関志望だった将来像は揺らぎ、『教育そのものを変えること』への関心が強まっていいきました。オンライン教育やテクノロジー活用型学習の可能性に惹かれ、海外大学院進学を目指したのですが、結果は全敗。卒業を目前にして進路は白紙となり、再び大きな挫折を味わいました」(永嶋さん)
 大学卒業時、現在の奥様(写真左)と指導教官(写真右)との一枚(写真提供=永嶋知紘)
大学卒業時、現在の奥様(写真左)と指導教官(写真右)との一枚(写真提供=永嶋知紘)
卒業後は日雇いや派遣の仕事を3か月ほど転々とし、将来像を描けない日々が続いた。精神的にも追い込まれる中、オープンエデュケーションに関わる専門職員の募集を見つけ応募。教材制作やオンライン教育支援に携わらないかという仕事内容であった。札幌へ移住し、現場で実務に向き合う2年間が始まる。
 当時永嶋さんが務めた北海道大学の職場前の風景(写真提供=永嶋知紘)
当時永嶋さんが務めた北海道大学の職場前の風景(写真提供=永嶋知紘)


永嶋さんが当時家族と毎日のように通っていた自宅近くのカフェでの様子(写真提供=永嶋知紘)
「当時お付き合いをしていた現在の妻も札幌についてきてくれました。この時期に初めて、教育をつくる側に立つことができ、この実践経験が、この後の道を作る大切な土台となりました」(永嶋さん)
家族と挑んだ研究者人生とドイツという選択
北海道大学での実務経験を経て、永嶋さんは再び海外へ挑戦する決意を固める。教育とテクノロジーを本格的に横断し、「学びを設計する力」を理論と実践の両面から深めたい。その思いから進学先に選んだのが、スタンフォード大学教育大学院だった。学習のためのテクノロジー開発、プログラミング、デザイン思考。教育を「教える側」ではなく、「つくる側」として捉え直すカリキュラムは、まさに求めていた環境だったという。
 スタンフォード大学のキャンパスの雰囲気(写真提供=永嶋知紘)
スタンフォード大学のキャンパスの雰囲気(写真提供=永嶋知紘)
 永嶋さんが尊敬する研究者 John Seely Brownさんとカリフォルニア自宅にて(写真提供=永嶋知紘)
永嶋さんが尊敬する研究者 John Seely Brownさんとカリフォルニア自宅にて(写真提供=永嶋知紘)
だが、この挑戦は決して一人のものではなかった。妻、そして生後9か月の長男と共に渡米するという選択は、理想と同時に現実を突きつけるものでもあった。「学費、生活費、住居。奨学金や限られた貯金の中で、生活は常に綱渡りでした。お金の話は、避けて通れなかったですね。家計の見通しが立たない中で、夫婦で何度も話し合いを重ねました」(永嶋さん)
「本当にこの道でいいのか」「日本に戻った方がよいのではないか」。議論は一度や二度ではなかった。将来のキャリアだけでなく、子どもの安全や教育環境、家族としての幸せとは何か。そのすべてを天秤にかけながらの決断だった。永嶋さんは当時を振り返り、「正解が見えない中で、選び続けるしかなかった」と語る。
 スタンフォード大学教育大学院 修士課程の最後のプロジェクト展示会の様子(写真提供=永嶋知紘)
スタンフォード大学教育大学院 修士課程の最後のプロジェクト展示会の様子(写真提供=永嶋知紘)
スタンフォードでの1年間は、学びの密度という点では濃密だったが、同時に限界も感じていた。幅広く学んだ一方で、研究として深く掘り下げる時間は足りない。「このままでは中途半端に終わる」。そう感じた永嶋さんは、さらなる探究を求めてカーネギーメロン大学の博士課程へ進学する。AI、機械学習、心理学、学習科学が高度に交差する環境で、個別化学習や学習分析、AIを用いたテクノロジーの設計と開発等をテーマに研究を進めていった。

カーネギーメロン大学 キャンパスのモニュメント前での一枚(写真提供=永嶋知紘)
 当時、永嶋さんが住んでいたアパート前の広場。子供たちはここでよく遊んでいたんだそう(写真提供=永嶋知紘)
当時、永嶋さんが住んでいたアパート前の広場。子供たちはここでよく遊んでいたんだそう(写真提供=永嶋知紘)
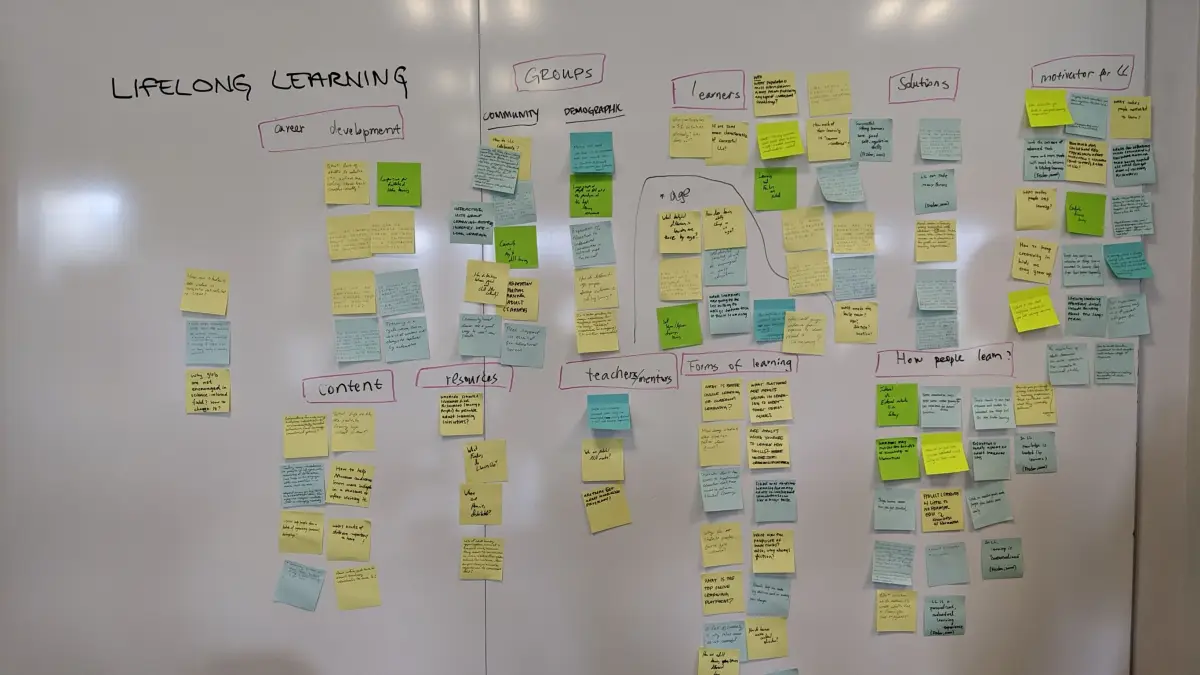 カーネギーメロン大学では、写真のようにポストイットを使ってアイデアをブレインストーミングしたり、分析したりしていたという(写真提供=永嶋知紘)
カーネギーメロン大学では、写真のようにポストイットを使ってアイデアをブレインストーミングしたり、分析したりしていたという(写真提供=永嶋知紘)
しかし、博士課程での生活は、理想とは程遠い現実の連続だった。博士課程の給与は限られており、家族4人を支えるには十分とは言えない。治安の良くない地域に住まざるを得ず、「週に一度は銃声が聞こえる環境だった」という。妻はビザの関係で自由に働くことができず、経済的な不安は常につきまとった。お金の話題は、再び夫婦の間で何度も議論の俎上に載った。
 永嶋さんはカフェ好きで、家からすぐの場所にあるカフェにいて作業する時間も多かったという。博士論文を書いたのもほとんどここだそう(写真提供=永嶋知紘)
永嶋さんはカフェ好きで、家からすぐの場所にあるカフェにいて作業する時間も多かったという。博士論文を書いたのもほとんどここだそう(写真提供=永嶋知紘)
日本への帰国という選択肢も、決して机上の空論ではなかった。実際に就職活動も行い、面接も受けた。「ただ、そのたびに心のどこかで引っかかりが残ったんです。ここでやめたら、後悔する気がしましたし、そんな私を妻も辛抱強く支えてくれました。二人目の子どもも生まれ、コロナ禍を家族で一緒に生きていく中で、最初は自分一人の夢だった海外での挑戦が、家族でチームとして挑戦しているんだという気持ちに変わりました」(永嶋さん)
研究者として、まだ問いを掘り切れていない。世界で通用する仕事ができるかどうかを、自分自身で確かめきれていない。その思いが、再び背中を押した。
博士課程修了が近づいた2022年、永嶋さんは進路を世界中に求めた。日本、アジア、欧州。数多くの公募に応募する中で出会ったのが、ドイツ・ザールラント大学だった。コンピュータ・サイエンス分野で国際的な評価が高く、学校現場における教育実践と研究者の距離が近い点に惹かれたという。そして選択にあたり、「研究者として」だけでなく、「家族として」生活しやすい環境も重視したという。
「ドイツは良い意味でアメリカと日本の間のような国です。世界最先端の研究環境に身を置き集中しながら、皆プライベートも大事にするので家族との時間も十分に確保できる。そのバランスが、今後の人生を考えたときに最も現実的だと感じました」(永嶋さん)
永嶋さんは家族とともにドイツへ移る決断を下した。