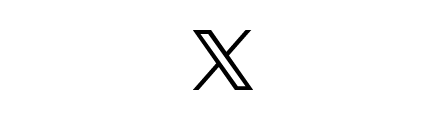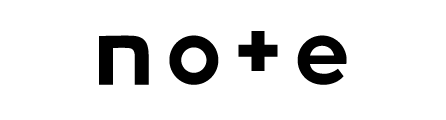- 総合TOP
- 宇宙
- AI
- ロボット
- WEB3・メタバース
「子どもの声に耳を傾けるだけで社会は変わる」。そう語るのは、「こども万博」を仕掛ける手塚 麻里さん。2022年に自宅の一室から始まった活動は、3年間で全国に拡大。大阪・関西万博内開催された同イベントでは、予定の5倍近くの2.4万人超の来場者を集めた。「こども万博」は、もはや単なるイベントではない。子ども自身が意思を持ち、社会とつながりながら成長していくプロセスそのものが価値となっている。手塚さんが大阪・関西万博を通じて感じた「子どもが社会とつながるポテンシャル」とは。(文=JapanStep編集部)

株式会社Meta Osaka 取締役 こども万博実行委員会委員長
株式会社こどもCandy 代表取締役
手塚 麻里さん
「親でも学校でもない場所」の重要性
「こども万博」を手掛ける手塚 麻里さんが子どもに関わる事業へ転じた理由は、医療関係で11年間勤務した経験に遡る。救命救急やクリニックで働くなかで、人の生活や感情に近い距離で関わってきた。だが医療は、目の前の人を支える仕事である一方で、本人の生活背景や成育環境まで深く踏み込むことは難しい。
その後、インターナショナルスクールでスクールナースとして働き、翌年には担任として子どもたちと向き合う機会を得た。そこでは、保護者が熱心に教育へ関与しているにも関わらず、まだ幼い子どもたちがが「親には言えないことがある」と打ち明ける姿を目にした。手塚さんは、子どもには家庭でも学校でもない第三の関係性が必要だと感じるようになる。
この視点には、彼女自身の原体験がある。中学期に家庭の事情により約2年間のホームレス生活を経験した。生活の不安だけではなく、「自分を見てくれる他者が存在するかどうか」が生きる支えになることを痛感したという。「困難な状況でも、声をかけてくれる大人がいるだけで未来の選択肢が変わる」。この実感が、子どもの第3の居場所という考えにつながっている。
2022年、株式会社こどもCandyを設立するきっかけとなったのは、芸人・絵本作家・オンラインサロン運営など、マルチに活躍する西野亮廣さんが全国に展開した「スナックCandy」だった。大人が夢を語る場所という概念を知り、「子どもにこそ夢を語る場所が必要だ」と考えた手塚さんは、直談判の末に「子ども版スナックCandy」として許諾を得た。関係性がフラットな空間をつくる。このシンプルな考えが、のちの「こども万博」の原型となった。
 株式会社こどもCandyが運営する少人数制のアフタースクール・学習塾は「今よりほんのちょっと素敵な世界を次の世代へ」をミッションに掲げる
株式会社こどもCandyが運営する少人数制のアフタースクール・学習塾は「今よりほんのちょっと素敵な世界を次の世代へ」をミッションに掲げる
特徴的なのは、受け入れの枠を設けなかったことだ。一部の学童保育で断られてしまうような子ども積極的に受け入れた。看護師として医療行為に対応できる経験があるからこそ、壁をつくらずに済んだという。「既存の枠からこぼれてしまう子どもたちも、大きな可能性を持っている。子どもは壁なんて気にしていない、教えているのは大人」という考えがその根底にある。
 子どもたちも能動的に参加できるサードプレイスになっている
子どもたちも能動的に参加できるサードプレイスになっている
子どもの意思が推進力となり、社会を巻き込むプロジェクトへ
「こども万博」は、自宅の一室で12人の子どもたちが128個の夢を書き出すところから始まった。当初は、子どもの内面を見つめる小さな取り組みだった。しかし、活動は予想を超える速さで拡大する。主役は常に子どもであり、大人はサポートに徹する。この構造が、多くの人の関わりを呼び込む要因となった。
 「こども万博」での手塚さんの様子
「こども万博」での手塚さんの様子
例えば、こども縁日では「親は一切口を出さない」というルールがある。大人が答えを与えないことで、子ども自身が状況を判断し、行動する必要が生まれる。来場者が少ない時間帯があっても、大人が助けない。子どもたちは自分たちで話し合い、看板をつくり、呼び込みを行う。体験の過程で、自分の判断で動ける手応えを掴んでいく。
 「こども縁日」の一コマ。運営側も参加側もとても楽しそうだ
「こども縁日」の一コマ。運営側も参加側もとても楽しそうだ
活動が広がった背景には、印象的な出来事がある。チラシを3,000枚印刷した際、日付を誤って印刷してしまうミスが起きた。大人が落ち込むなか、子どもが「捨てるのはもったいない」と提案し、修正テープで直し始めた。やがてその姿がSNSで共有され、主婦、学生、会社員などがボランティアとして集まり、最終的にはポスティング会社まで協力に加わった。子どもの主体性に、大人が動かされた象徴的な場面である。
こうした積み重ねにより、こども万博は地域に根ざした取り組みから全国規模へと拡大し、累計動員数は9万5千人を超えた(2025年時点)。短期間で広がった背景には「誰かが与える」のではなく、「子どもが動き、周囲の大人を巻き込む」という構造がある。子どもが動き、大人が動かされ、地域が変わっていく。その循環が、プロジェクトを単なるイベントから社会実装へと変えていった。
万博が照らす「子どもが社会とつながる時代」の未来
2025年10月、大阪・関西万博。EXPOメッセ WASSEで「こども万博」が開催された。未就学児から小学生を中心に、国内外からの来場者を含め、当初の5倍超の2万4千人規模に達した。
 子ども自らが自信をもって夢を語る。こうした経験が子供の「考えるプロセス」を生み出す
子ども自らが自信をもって夢を語る。こうした経験が子供の「考えるプロセス」を生み出す
会場では、子どもが店長として運営する縁日、夢を語るステージなどが実施された。ここでも一貫して「大人が答えを与えない」という方針が貫かれた。多国籍の来場者を前に、子どもは自分の言葉で説明する。英語が話せなくても、相手の目を見て、身振り手振りで伝えようとする。伝わらない時間があることも含めて、子どもは「考えるプロセス」を体験する。
手塚さんは、日本の教育文化に課題意識を持っている。「日本の教育は、いまも『正しい答えを導くこと』に重きが置かれています。テストで点を取るための学びが中心で、自分の意見を言葉にする機会は限られてしまう。一方、海外では『あなたはどう思う?』と問われ、考えを根拠とともに伝える力を育てることが重視される。実際、我が子たちも、日本の学校では先生が自分の気持ちをあまり話さず、子どもたちも本音を言いづらいと感じていた。そして、いろんな考えを知り、語り合える環境を求めて海外の学校へ通い始めました。」(手塚氏)。
正解に合わせるのではなく、自分の考えを持つことが重視される環境こそが、将来の不確実性に対応できる力を育てるという考えだ。万博の現場でも変化が見えた。イベント終了後、子どもたちから自然とこんな声があがった。
「次の万博は、どの国で開かれるの?」「海外でも、こども万博をしてみたい。」
これは、単なる感想ではない。万博という「地球の縮図」を体感したことで、子どもの世界認識が変わったことを示している。手塚さんによれば、今後「こども万博」を海外で展開する動きを進めているという。挑戦の舞台は、国内の地域から国際社会へと広がりつつある。
 「『こども万博』は地域によって違いが出るのも面白い」と手塚さん。子どもの主体性から次はどんなアイデアが形になるのだろうか
「『こども万博』は地域によって違いが出るのも面白い」と手塚さん。子どもの主体性から次はどんなアイデアが形になるのだろうか
「こども万博」では、参加経験を重ねた子どもが「子どもスタッフ」として企画や運営に関わる制度が導入されている。一定の経験を積んだ子どもは、海外イベントへ同行するチャンスが得られる。挑戦が単発の経験に終わらず、次の機会につながる設計である。
手塚さんが繰り返した印象的な言葉がある。「子どもの声に耳を傾けるだけで、社会は変わる。」
理念ではなく、万博というグローバルな舞台でも実証された事実だ。「こども万博」は、子どもを保護の対象とするのではなく、社会に参加する主体として扱う「新しい社会実装」のひとつのモデルケースになるかもしれない。
編集後記
手塚さんのお話はまさに「熱量の塊」。子どもたちとのエピソードは面白く、興味深いものばかりで、取材時間があっという間でした。取材を通じ、「こども万博」は子どもが自らの意思で社会につながり、自分の言葉を持つための場であると改めて感じることができました。大阪・関西万博という世界的な舞台で、子どもが「参加者」ではなく「当事者」になった。この成功体験は、未来の日本を担う子どもたちの財産になったと思いますし、「こども万博」のモデルは、教育や自治体、企業が直面する課題に対して新たなヒントを与えてくれるように感じました。(ちなみに取材後、今後のJapanStepとの連携についても大いに盛り上がりました)。