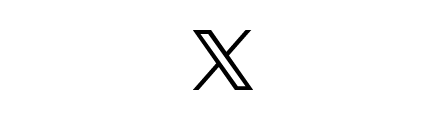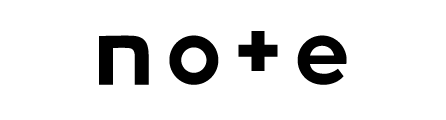- 総合TOP
- 宇宙
- AI
- ロボット
- WEB3・メタバース
池袋・サンシャインシティの噴水広場。数多のアーティストやアイドルが登竜門として立ち、熱狂を巻き起こしてきたその場所に、2025年12月、これまでとは質の異なる火花が散った。ステージ上で繰り広げられたのは、手作りの応援グッズが揺れる中で放たれる、緻密なロジックとプログラミングスキルの応酬だ。
「全国小学生プログラミング大会 ゼロワングランドスラム2025」。約1,200名の予選を勝ち抜いた精鋭たちが挑んだのは、単なる知識の蓄積を問うテストではない。仲間と知恵を絞り、一分一秒を争う「勝負」の舞台だ。そこには、野球やサッカーと同じ熱量で「日本一」を志す、新しい時代の挑戦者たちの姿があった。(文=JapanStep編集部)
戦略と連携が生んだ熱戦。競技としてのプログラミング

(引用元:PR TIMES )
2025年12月7日に開催された決勝大会には、WEB予選から勝ち上がった12名の小学生プログラマーが集結した。この大会の特筆すべき点は、プログラミングを「個人の習い事」の枠から解き放ち、チームで戦う「競技スポーツ」へと昇華させている点にある。
第一種目のロボット競技『スクランブルバトル』は、その象徴だ。プログラムによって自律移動するロボットを操り、フィールド上のブロックを運んで得点を競う。しかし、単に正確に動かすだけでは勝てない。同一フィールド上で対戦相手と戦うため、相手の動線を読み、時には「おじゃまブロック」を配置するといった高度な戦略的判断が求められる。子どもたちはモニターを見つめ、刻々と変わる状況に対してリアルタイムで戦術を修正していく。そこにあるのは、まさにトップアスリートさながらの集中力だ。

(引用元:PR TIMES )
さらに審査員たちを驚愕させたのが、第二種目の『ゼログラハッカソン』である。ビジュアルプログラミングツール「Scratch」を用い、3名1組でリレー形式のゲーム開発を行う。与えられた時間は作戦タイムを含めてわずか45分。その場で発表される「ペンギン」や「ほうき」といった特定の素材(スプライト)を必ず使い、一つの完成されたゲームを創り上げなければならない。
 (引用元:PR TIMES )
(引用元:PR TIMES )
この極限の条件下で、西日本代表「チーム700系」が見せた独創的なシューティングゲームや、総合優勝を果たした東日本代表「プログラマスターズ」の安定した開発能力は、専門家をも唸らせるレベルに達していた。特に、自分たちのミスをカバーし合い、役割を全うする姿は、プログラミングが「孤独な作業」ではなく、高度な「コミュニケーション能力」と「信頼」の上に成り立つものであることを雄弁に物語っていた。
これからの日本が彼らから受け取る「挑戦」の種
2026年、プログラミング教育はもはや「新しい教科」の一つというフェーズを越え、次世代を担うイノベーターたちの「共通言語」へと定着しつつある。このゼロワングランドスラムという大会が社会に提示しているのは、単なるスキルの優劣ではない。正解のない問いに対して仲間と共に立ち向かい、限られたリソースで最大の結果を出すという、ビジネスの最前線でも通用する「生きる力」の育成だ。
会場には、ヤマハ発動機、Cygames、Microsoft といったテクノロジー企業のリーダーたちが審査員として名を連ねた。また、後援には文科省、経産省、デジタル庁、そして各地の教育委員会が並ぶ。この重厚なバックアップ体制は、彼ら「デジタル・アスリート」が、将来の日本経済を再起動させる重要な資産であることを物語っている。

(引用元:PR TIMES )
甲子園の土を踏む姿に憧れて多くの子どもたちが白球を追いかけるように、池袋の噴水広場でキーボードを叩き、ロボットの挙動に一喜一憂するファイナリストたちの姿は、画面越しの数万人の子どもたちにとっての「憧れ」へと変わるだろう。この「憧れの連鎖」こそが、日本のデジタル競争力を根底から支える源泉となる。
競技を終えた子どもたちが、勝敗に関わらずお互いの健闘を称え合い、協力してくれたチームメイトに感謝を伝える場面が見られた。技術という武器を持ちながら、その根底には人間としての温もりが通っている。
彼らが2026年、そしてその先の未来においてどのような「挑戦」を続けていくのか。その足取りを社会全体で見守り、育んでいく必要がある。12名のファイナリストが見せた情熱は、効率化や合理性ばかりを追い求める大人たちに対し、「創造することの純粋な喜び」という原初的な挑戦の価値を問い直している。